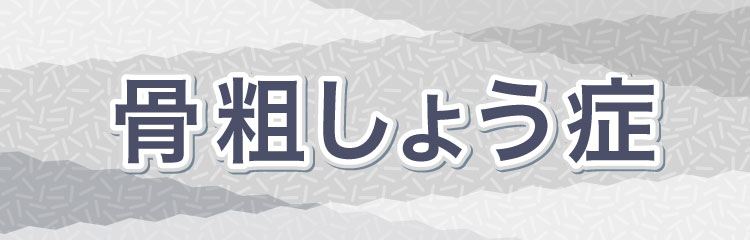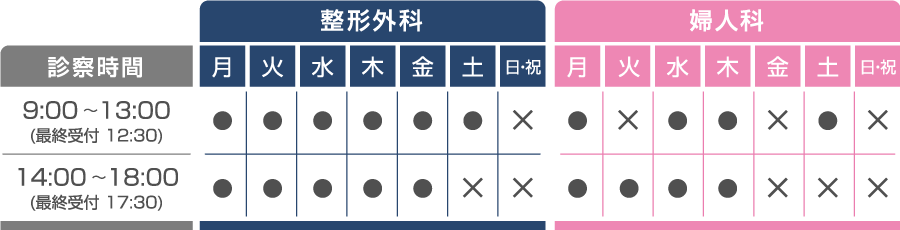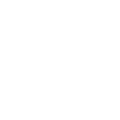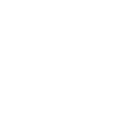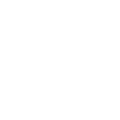福岡市早良区西新の整形外科、婦人科「かなざわ整形外科・婦人科」
整形外科
整形外科について
整形外科は、四肢の骨、関節、筋肉、靭帯、腱、脊髄、末梢神経を対象とした病気や外傷による症状を機能的に改善する診療科です。
全身を対象としており、幅広い年齢層の患者様の診察にあたります。当院では、患者様ひとりひとりにあった治療をご提案させていただきます。
下記のような項目に当てはまる方はお気軽にご相談ください。
全身を対象としており、幅広い年齢層の患者様の診察にあたります。当院では、患者様ひとりひとりにあった治療をご提案させていただきます。
下記のような項目に当てはまる方はお気軽にご相談ください。
こんな症状はありませんか?
- 首が痛い
- 肩が痛い/上がらない、肩こり
- 手、足がしびれる
- 手、肘が痛い、腫れている
- 関節がこわばる、腫れている
- 腰が痛い
- 膝、股関節が痛い、腫れた
- 足首のいたみ
- 捻挫、脱臼、骨折
- 怪我(切り創/挫創も含む)
- 交通事故、仕事中(労災)のけが
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
肩に原因不明の炎症が起こり、肩を動かしたときに痛みが生じます。だんだんと炎症が広がると痛みがつよくなり、肩の動き(可動域)も悪くなります。はじめは手を後ろに回す動作で痛みを感じることが多いですが、悪化するとじっとしていても痛くなり(安静時痛)、夜寝ていても痛みを感じ、痛みで目が覚める、眠れないということもあります(夜間痛)。肩の動きが悪くなり、肩こりも起こりやすくなります。
症状
初期は肩を動かしたとき、動きの最後で痛みを感じます。しかし、肩の動きがあまり悪くないためテニスやゴルフなどスポーツが普通にできることも多いですが、肩の動きが悪くなってくると、スポーツ活動や、日常生活に支障がでてきます。肩の動きが悪くなるにつれ痛みが強くなってくるのがこの病気の特徴で、症状が進行してくると動かしたときの痛みだけでなく、安静時痛や夜間痛も現れるようになります。
原因
医学的な原因ははっきりしていません。肩の筋が切れたり(腱板断裂)、石灰がたまったり(石灰沈着性腱板炎)して似たような症状が出ることがありますが、純粋な四十肩・五十肩は基本的に何も悪くないのに発症します。
診断・検査
痛みの箇所、肩関節の動き(可動域)の制限の評価を行います。場合によっては、腱の断裂や頸椎・神経の疾患がないかを詳しく調べるためにレントゲン検査(X線検査)や超音波検査(エコー)、必要に応じてMRI検査を行います。
治療
メインは薬物療法で、痛みに対して痛み止めの処方や注射を行います。自然に治ってしまうこともありますが、多くの場合放っておくと症状が悪化します。また肩の動きを戻していくためのリハビリが大切です。
予防
肩のストレッチを行い、肩の動き(可動域)を維持することが大切です。スポーツができていても四十肩・五十肩になっている場合もありますので、普段から肩をしっかり動かし、自分の肩の動きをしっかりと知っておきましょう。
ロコモティブシンドローム(ロコモ)
超高齢社会を見据え、日本整形外科学会が2007年に提唱した、運動器の障害で、身体能力(移動機能)が低下した状態を 「ロコモティブシンドローム(ロコモ、または運動器症候群)」といいます。進行すると、将来、介護が必要になるリスクがあがります。ロコモ度テストを用いた住民調査から、ロコモと判定されるロコモ度1以上の人は4590万人と推定されています(※)。
日常生活に支障はないと思っていても、ロコモになっていたり、すでに進行したりしている場合が多くあることが分かっており、いつまでも健康に歩き続けるために、ロコモの予防、進行を抑えて運動器を長持ちさせることで、健康寿命を延ばしていくことが大切です。
日常生活に支障はないと思っていても、ロコモになっていたり、すでに進行したりしている場合が多くあることが分かっており、いつまでも健康に歩き続けるために、ロコモの予防、進行を抑えて運動器を長持ちさせることで、健康寿命を延ばしていくことが大切です。
※日本整形外科学会,日本運動器科学会:ロコモティブシンドローム診療ガイド2021,文光堂,2021,p.20
ロコモを防ぐには、日本整形外科学会に所属している専門医のもとで治療を受けることが大切です。
当院院長は、日本整形外科学会専門医であるとともに、ロコモアドバイスドクター、がんロコモドクターとして登録されております。ロコモアドバイスドクターとは、ロコモティブシンドロームの正しい知識と予防意識の啓発のための活動を行なっている日本整形外科学会所属の専門医です。がんロコモドクターとは、ロコモアドバイスドクターおよびサポートドクターのうち、「がんロコモ」について詳しく相談にのれる医師です。
当院院長は、日本整形外科学会専門医であるとともに、ロコモアドバイスドクター、がんロコモドクターとして登録されております。ロコモアドバイスドクターとは、ロコモティブシンドロームの正しい知識と予防意識の啓発のための活動を行なっている日本整形外科学会所属の専門医です。がんロコモドクターとは、ロコモアドバイスドクターおよびサポートドクターのうち、「がんロコモ」について詳しく相談にのれる医師です。
ロコモ度テスト
1.立ち上がりテスト
2.ステップテスト
3.ロコモ25
2.ステップテスト
3.ロコモ25
変形性関節症
関節表面を覆う関節軟骨が、機械的刺激などにより軟骨の変性・磨耗を生じ、関節周囲を取り囲む滑膜といわれる膜状の組織の炎症が併発して変性が進行します。さらに関節周囲の骨軟骨形成などの増殖性変化を伴い変形がすすんでいきます。それらの変化により血管増生や神経線維の増生をともなう関節包の線維化が起こることで痛みが感じやすくなります。
関節の中では、とくに体重がかかる関節(荷重関節)として膝関節、股関節の関節症が問題となります。また、上肢では手を使うお仕事をされている方の肘関節がしばしば問題となります。50歳以上の1000万人が変形性膝関節症による膝痛を経験しているといわれており、
症状は、関節炎に伴う痛みと腫れ、それに伴う可動域制限が生じます。軟骨の磨耗の進行により関節炎が起こりやすくなり、荷重の繰り返しにより痛みを感じやすくなります。 軟骨が消失するとある程度以上の荷重刺激により痛みを感じ、その繰り返しにより、徐々に悪化していきます。さらに広範囲の軟骨が消失すると関節への負荷により痛みをかんじやすくなり、可動域がますます制限され、関節拘縮を起こしやすくなります。
原因は、年齢によるもの、原因不明のもの、種々の炎症性の疾患、軟骨脆弱性、外傷、関節形成不全、関節動揺性など様々なものが、関節症発症の原因となりえます。
関節の中では、とくに体重がかかる関節(荷重関節)として膝関節、股関節の関節症が問題となります。また、上肢では手を使うお仕事をされている方の肘関節がしばしば問題となります。50歳以上の1000万人が変形性膝関節症による膝痛を経験しているといわれており、
症状は、関節炎に伴う痛みと腫れ、それに伴う可動域制限が生じます。軟骨の磨耗の進行により関節炎が起こりやすくなり、荷重の繰り返しにより痛みを感じやすくなります。 軟骨が消失するとある程度以上の荷重刺激により痛みを感じ、その繰り返しにより、徐々に悪化していきます。さらに広範囲の軟骨が消失すると関節への負荷により痛みをかんじやすくなり、可動域がますます制限され、関節拘縮を起こしやすくなります。
原因は、年齢によるもの、原因不明のもの、種々の炎症性の疾患、軟骨脆弱性、外傷、関節形成不全、関節動揺性など様々なものが、関節症発症の原因となりえます。
変形性膝関節症
変形性膝関節症とは、軟骨部分がすり減り、炎症や変形が生じて、膝に痛みが生じる病気です。男女比は1:4で女性に多いことが分かっています。変形性膝関節症は、ロコモティブシンドローム(ロコモ)の原因となる疾患の1つで、変形性膝関節症による膝の痛みを抱えている人は、国内だけでも推定1,000万人にも上ると言われています。
変形性膝関節症の原因
性別と年齢
変形性膝関節症は、基本的に加齢に伴って起こる疾患です。一般的に40歳前後から始まるとされており、50代から60代での発症が多く、男性よりも女性の方が発症する割合が多いといわれています。要因の一つとして、加齢の影響で、膝周りの筋力が低下してくることが挙げられます。
体重と体質
変形性膝関節症による軟骨の変化は、内側に起こりやすく、多くが膝の内側の痛みを訴える方が多いです。下肢は、O脚変形が生じやすくなります。また、肥満の方はそれだけ膝への負荷が大きく、発症や増悪に関係していると考えられています。また、閉経後の女性のホルモンバランスの影響を指摘する研究結果もあります。
変形性膝関節症の症状
変形性膝関節症の主な症状は、膝の痛み(内側が多い)と水がたまることです。また、症状の段階によって重症度も異なります。
初期
立ち上がった時や歩き始めるときなどの膝を動かし始めたときに痛みが生じますが、安静にすることで痛みは改善し、その程度も軽度です。
進行期
初期に比べて痛みの頻度や程度が増悪し、正座やしゃがみこんだ時、階段の昇り降りがつらくなり、膝関節の動きが一部制限をされる状態です。
末期
膝が完全に曲がらない・伸びきらない状態になり歩行が困難となり日常生活に支障をきたすようになります。
変形性膝関節症の検査
レントゲン検査(X線撮影)で、膝関節の状態を観察します。必要に応じて骨壊死や関節炎(可能性関節炎、偽痛風)などを調べるために、MRI検査・関節液検査・血液検査を行う場合があります。
変形性膝関節症の治療
症状が軽い場合は、痛み止めの内服薬や外用薬の処方、膝関節内にヒアルロン酸の注射などをします。また、水が溜まっている場合は、水を抜きます。また、症状緩和にはリハビリテーションも有効で大腿四頭筋の強化や関節可動域の改善を目的にリハビリを行います。、膝を温めたりする物理療法を行います。
また、足底板などの装具療法も効果的です。
これらの治療で改善が見られない場合は、関節鏡手術や人工膝関節置換術などを行う場合があります。
変形性膝関節症の予防
- 体重のコントロール。適正体重を維持し、不必要な体重増加を避ける。
- 痛みがある場合は、痛みを伴う動作をさけて膝への負担軽減に努める。
- 膝を温めて血行を良くする。
- 運動療法によって膝周辺の筋力を強化し、膝関節の負担を軽減します。
- 体幹筋を鍛えてバランス能力を上げること、膝への負担が軽減されます。
おすすめの自分でもできる運動
SLR(脚上げ体操)
- 仰向けで寝転び、片方の膝を立てて、もう片方の脚を伸ばします。
- 伸ばしている脚を地面から10~20センチ程度上げて、ゆっくり伸ばしている脚を元に戻します。
- 左右の脚を入れ替えて、繰り返し行いましょう。(3セット程度)
大腿四頭筋訓練
- 椅子に腰かけ、背筋を伸ばし、片方の脚をまっすぐになるよう浮かせて、5~10秒間静止しましょう。
- ゆっくり伸ばしている脚を元に戻しましょう。
- 左右の脚を入れ替えて、繰り返し行いましょう。(3セット程度)
変形性股関節症
日本の患者様の多くは女性です。原因は発育性股関節形成不全の後遺症や股関節の形成不全といった子供の時の病気や発育障害の後遺症が主なもので股関節症全体の80%といわれています。最近は高齢社会となったため、特に明らかな原因が無くても年齢とともに股関節症を発症してくることがあります。
変形性股関節症の症状
股関節症の主な症状は、鼠径部(脚の付け根)の痛みと機能障害です。初めは立ち上がりや歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。
関節症の進行に伴い、その痛みが強くなり、場合によっては痛みが持続したり、夜間痛で悩まされることがあります。
一方日常生活では、足の爪切りがやりづらい、靴下が履きにくい、和式トイレ使用や正座が困難など不便になってきます。また長時間立ったり歩いたりすることがつらくなるので、家事などの主婦労働に支障を来たします。階段や車・バスの乗り降りも手すりが必要になります。
変形性股関節症の検査
診断は、レントゲン検査(X線撮影)によって確定します。必要に応じて骨壊死などを調べるために、MRI検査を行う場合があります。
変形性股関節症の治療
本症と診断されたらまず股関節の負担を減らして大事に使うということが大切です。
痛みを伴う動きをしないというのが大切です。どのような動きで痛みが強くなるか?を自分自身で関節の調子を確認しながら、痛くないように生活を送ることが大切です。痛み止めのお薬を使うことも考慮されますが、できれば調子の悪い時やどうしても負担をかけなければならない時に限定して使うのが良いと思います。また、関節の負担を減らすという観点から、過体重があるようでしたら適正体重に減量することも必要です。心理的抵抗がなければ杖を使うことで関節への負担を減らすこともできます。
一方で、動きが少なくなることで筋肉が衰えてしまいますので、可能であれば、浮力によって関節への負担が少ない、水中歩行や水泳(平泳ぎを除く)を週2,3回行っていただくと理想的です。運動療法はどうしても疼痛を誘発してしまう可能性がありますので、慎重に始めて徐々に強度を高めていくことがポイントです。
これらの保存療法でも症状が取れない場合は手術療法を考えます。初期のうちでしたらご自身の骨を生かして関節を温存する切り術の適応もありますし、関節の変形が進行している場合は人工股関節手術の適応となります。当院では、痛みのコントロール、リハビリ指導を中心に行っております。手術適応やご希望の方は、専門の病院へご紹介させていただきます。骨切り術に関しては、手術のタイミングの判断が難しい場合がございます。特に福岡は、股関節手術を専門とする骨切り術のできる優秀なドクターがたくさんおられますので、手術に関してもなんなりとお尋ねください。
痛みを伴う動きをしないというのが大切です。どのような動きで痛みが強くなるか?を自分自身で関節の調子を確認しながら、痛くないように生活を送ることが大切です。痛み止めのお薬を使うことも考慮されますが、できれば調子の悪い時やどうしても負担をかけなければならない時に限定して使うのが良いと思います。また、関節の負担を減らすという観点から、過体重があるようでしたら適正体重に減量することも必要です。心理的抵抗がなければ杖を使うことで関節への負担を減らすこともできます。
一方で、動きが少なくなることで筋肉が衰えてしまいますので、可能であれば、浮力によって関節への負担が少ない、水中歩行や水泳(平泳ぎを除く)を週2,3回行っていただくと理想的です。運動療法はどうしても疼痛を誘発してしまう可能性がありますので、慎重に始めて徐々に強度を高めていくことがポイントです。
これらの保存療法でも症状が取れない場合は手術療法を考えます。初期のうちでしたらご自身の骨を生かして関節を温存する切り術の適応もありますし、関節の変形が進行している場合は人工股関節手術の適応となります。当院では、痛みのコントロール、リハビリ指導を中心に行っております。手術適応やご希望の方は、専門の病院へご紹介させていただきます。骨切り術に関しては、手術のタイミングの判断が難しい場合がございます。特に福岡は、股関節手術を専門とする骨切り術のできる優秀なドクターがたくさんおられますので、手術に関してもなんなりとお尋ねください。
上腕骨外側上顆炎(テニス肘)
上腕骨外側上顆炎とは、通称「テニス肘」とも言われ、長期に渡って肘の外側の筋肉を使い過ぎたことにより、肘の外側から前腕にかけて炎症が起こって痛みを生じる病気です。また、テニスだけでなく、バドミントンやゴルフなど肘や手首を使う他の競技でと発生するだけでなく、特にスポーツ活動を行ってない方もなることが多いです。
上腕骨外側上顆炎の症状
スポーツ活動や重い荷物を持つときなどに痛みを感じ、安静にしていると痛みは少ないですが、ひどくなってくると「物をつかんで持ち上げる動作」や「タオルを絞る」、「ドアノブを回す」などの日常生活でも痛みを生じるようになります。
上腕骨外側上顆炎の原因
肘には、手首を動かしたり指を曲げたり伸ばしたりする筋肉が存在しており、その中の一つに短橈側手根伸筋(たんとうそくしゅこんしんきん)という筋肉があり、その腱の部分に炎症が起きたときに起こりやすいと言われています。同じ動作を何度も繰り返すことで、過度の負担がかかり、この腱の部分に亀裂や炎症が起きて痛みが発生します。
上腕骨外側上顆炎の診断・検査
腱の炎症のためレントゲン検査(X線検査)では、骨の異常を確認することができませんが、ひどくなってくるとレントゲンで腱の部分に石灰化した所見を確認できることがあります。また、炎症や損傷の具合を超音波検査やMRIで調べることもありますが、ほぼ症状で診断できます。
有名な診断テストとして下記の3つがあります。
Thomesen(トムセン)テスト
肘を伸ばしたまま手首を上に反らした状態で、医師が手首に下向きの力を加えた時に痛みを生じるかを確認します。
Chair(チェア)テスト
椅子を持ち上げるときに、肘の外側に痛みを生じるか確認します。
中指伸展テスト
中指を下向きに押したときに、それに抵抗して中指を上に持ち上げようとしたときに、肘の外側に痛みを生じるか確認します。
上腕骨外側上顆炎の治療
治療は、患部(肘)だけでなく手指や手関節部を安静にし、お薬を併用する保存的療法が基本となります。
薬物療法
湿布などの外用薬や炎症を抑える消炎鎮痛剤(痛み止め)を服用します。
理学療法
温熱療法、レーザーなどの物理治療を行い、症状が軽くなってからは筋力トレーニングやストレッチなどのリハビリを行っていきます。
腰痛
整形外科の外来をしていてもっとも多く見られる痛みの一つです。腰痛が起きる原因は様々で、筋肉や靭帯の異常、椎間板や脊椎の異常があげられます。ときに、内臓の病気が原因であることもあります。症状に合わせ、ブロック注射療法、理学療法、運動療法、薬物療法などを組み合わせて、症状緩和のための治療を行いますが、原因の検索、確定診断も重要です。
腰痛を起こす原因となるものとして整形外科的に代表的なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
腰痛を起こす原因となるものとして整形外科的に代表的なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 急性腰痛症(ぎっくり腰)
- 腰部脊柱管狭窄症
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰椎変性すべり症
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 変形性腰椎症
- 腰椎圧迫骨折 など
原因検索のための検査としては、レントゲン検査をはじめとして、場合によってはMRIなどの検査をおすすめします。診断によっては、手術を必要とするもの、症状をコントロールしながら病気と付き合っていくものなど病気や、患者様の年齢や背景などによって様々です。
痛風
痛風は尿酸が体の中にたまり、それが結晶となり激しい関節炎を伴う症状になる病気です。
放置すると、激しい関節の痛みを繰り返したり、体に、しこり(結節)が出来たり、腎臓が悪くなったりする重大な病気でもあります。
痛風として症状が起きる前に血液の尿酸値が高い状態が長く続きます。これを高尿酸血症と言います。
痛風の症状と原因
放置すると、ある日突然、足の親指の付け根などの関節が赤く腫れ痛み出します。痛みは激烈で、耐え難いほどの痛みを生じます。文字通り、風が吹くだけでも痛みが発生するためにこの名前が命名されたといわれています。美食家に多く発病し、貴族の病とも言われていましたそうで、 フランスの皇帝ナポレオンも痛風に悩まされましたらしいです。発作的な痛みなのでそれを痛風発作と呼びます。10日程度で治まり、症状が落ちつきますが多くの場合、発作は再発します。親指の付け根だけでなく、肘、手首、膝などにも起こることもあり、慢性化すると節々が腫れ、手足の曲げ伸ばし等の日常動作に支障がでてきます。
血清尿酸値の高い人は心血管障害や脳血管障害のリスクが他の人より高いといわれています。これを防ぐためには尿酸値以外の動脈硬化のリスク因子にも注意する必要があります。
痛風は圧倒的に男性に多いのが特徴で、20歳以降に見られます。女性がかかりにくいのは、女性ホルモンが尿酸の尿中排泄を促すためです。しかし、女性ホルモンの分泌が減少する閉経後は、女性も痛風を発症しやすいので注意が必要です。
痛風の診断と検査
足の指などの痛みがある患者様で、痛風を疑った患者様には、採血で尿酸値を検査します。また、ひざなどの大きな関節の場合は、関節液を採取して関節益の検査を行うこともあります。
痛風の治療
痛風発作を起こされた方は、尿酸値のコントロールの前にまず炎症を治めることが必要です。抗炎症薬などを使用してまず、痛みと炎症のコントロールを行います。
健診などで尿酸値を指摘された方は、以下のような方針で治療をすすめます。
- 尿酸値が7.0mg/dlを超えている方は、まずは生活習慣を見直します。
- 尿酸値が9.0mg/dlを超えている、または、内科的な持病をお持ちの方で尿酸値が8.0mg/dlを超えている、痛風発作を起こしたことがある方は、内服薬によって尿酸値のコントロールが必要です。
- 尿酸値6,0mg/dl以下を保つと、体に沈着している尿酸の結晶が溶けだし、痛風発作や合併症のリスクが減るといわれているため、内服薬によって尿酸値6,0mg/dl以下をめざします。
スポーツ整形外科
スポーツ活動に伴う外傷や障害についての、治療・診断を行う診療科です。さまざまなスポーツについての運動内容や外傷・障害の特徴などを理解したうえで、運動療法、装具療法、リハビリテーション療法などによる総合的な治療を行います。基本的な症状やケガに対して行う治療は、他のケガや障害と重なる部分がありますが、患者様それぞれの目指すべきゴールが異なり、ケガの再発予防などスポーツ特有のものもあります。当院院長は、日本整形外科学会スポーツ医、日本医師会認定スポーツ医、日本体育協会公認スポーツドクターといったスポーツに関する資格を取得しています。
競技復帰や今後の障害予防など、競技者・選手に寄り添い、対応させていただきます。
競技復帰や今後の障害予防など、競技者・選手に寄り添い、対応させていただきます。
交通事故
交通事故の症状
交通事故直後は、症状がなくても数日経過した後に徐々に痛みが現れることがあり、慢性化する恐れもあります。事故にあわれた方は、一度検査を受けることをお勧めします。
交通事故の一般的な流れ
警察へ交通事故の届け出をする
警察から「交通事故証明書」が発行されます。被害者、加害者どちらの場合も警察への届け出を行います。
相手の情報を確認をする
相手の氏名、住所、連絡先、自賠責保険、自動車保険の会社名、車のナンバー等
保険会社へ連絡し、医療機関を受診
- 当院を受診することを保険会社へ連絡してください。その後、保険会社から当院へ連絡が来ます。この時点から当院での治療費は保険会社負担となります。(患者様の窓口負担はありません)
- 保険会社から連絡がない場合、治療費は一時的に自費(100%)でお支払いいただきますが、保険会社と確認が取れれば、返金いたします。
- 受付時に、交通事故で受診する旨をお伝えください。
検査、診断
必要に応じて処方いたします。
警察に診断書を提出
治療を受ける
通院し、リハビリを行います。
治療終了
治癒または症状固定
労災
当院は労災保険指定医療機関です。
業務中や通勤途中に事故やケガをされた際には、勤務先の必要書類をご確認の上受診をしてください。
業務中や通勤途中に事故やケガをされた際には、勤務先の必要書類をご確認の上受診をしてください。
労災で医療機関にかかる際の注意点
労災申請をして認定されれば療養費は労災保険が適用されますので、必要な書類があれば患者様負担はありません。まずはお勤め先に労災保険に加入しているかどうかご確認ください。
労働災害(労災)から治療まで一般的な流れ
勤務先に報告
勤務先へ報告します。
書類提出
労災申請書を労働基準監督署宛てに提出します。(勤務先または、患者様から)
認定
労災認定後に「療養の給付申請書」を持参してください。受診当日から窓口負担金は無料となります。(サポーター代、包帯代、診断書代等は除く)
労災未確定の場合
※労災扱い未確定の方は、確定するまで自費となります。労災認定確定後、「療養の給付申請書」をお持ちください。自費徴収分が全額返金されます。
よくある質問
- アルバイトでも労災は使えますか?
- 正社員・契約社員・パート等の種類は全く関係ありませんので勤務先に確認してください。
リハビリテーション
当院では、幅広い年齢層の幅広いお悩みに対応したリハビリテーションに力を入れています。
患者様の生活の質を上げ、健康寿命を延ばすことを目標に、医師と理学療法士がチームとなり、患者様のリハビリをサポートいたします。また、最新のリハビリ機器を導入しており、体の動かしづらさや痛みを改善できるリハビリプランも患者様お一人お一人に合わせてご提案いたします。お気軽にご相談ください。
患者様の生活の質を上げ、健康寿命を延ばすことを目標に、医師と理学療法士がチームとなり、患者様のリハビリをサポートいたします。また、最新のリハビリ機器を導入しており、体の動かしづらさや痛みを改善できるリハビリプランも患者様お一人お一人に合わせてご提案いたします。お気軽にご相談ください。
骨粗しょう症
骨粗しょう症は、早期発見早期治療が非常に重要です。高齢化社会に伴い、骨粗しょう症患者様は年々増加している一方で、実際に治療に取り組んでいる患者様は少ないのが現状です。骨折してしまってからではなく、骨折しないための骨粗しょう症治療をご提案しております。特に、女性は年齢とともに骨密度の低下が著しく進んでしまうため、早めのご相談をおすすめしています。当院では、婦人科とも連携して検査や治療を行うことができます。